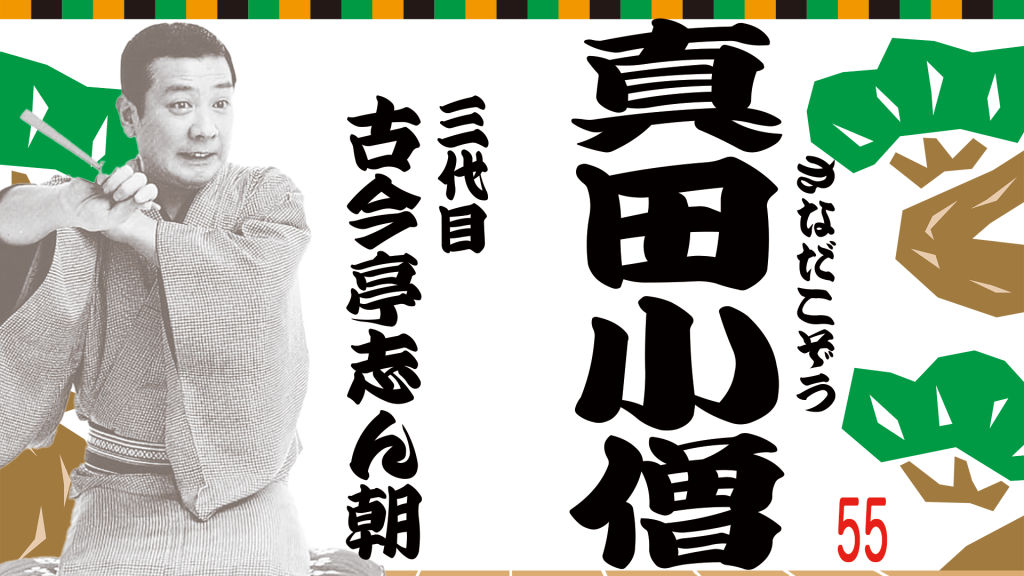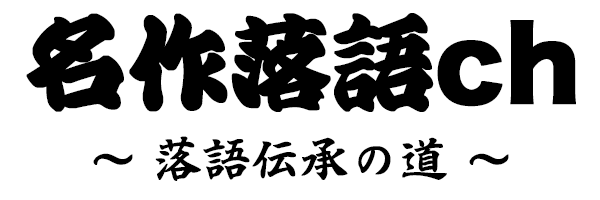◎あらすじ◎
落語「真田小僧」は、子どものずる賢さと親の滑稽さを描いた滑稽噺(こっけいばなし)で、江戸の市井の家庭を舞台にしたユーモアと機知に富んだ物語です。
物語は、主人公の亀坊という少年が、父親の熊さんに小遣いをねだるところから始まります。熊さんは断るものの、亀坊は「お母っさんに言えばくれるよ。だってこの間、あんたが留守のときに知らない男の人が来てたから」と意味深なことを言います。その一言で熊さんは不安になり、詳しく聞こうとしますが、亀坊は「話の続きを聞くには前払いが必要」と、まるで寄席の木戸銭のように金を要求します。熊さんは渋々5円を渡します。
亀坊は話を続け、「お母っさんは男の人の手を取って、『うちのがいなくてちょうどよかった』って言って、座敷にあげた」と語ります。熊さんはますます動揺し、次の展開を知りたがりますが、亀坊は「ここからは大事な場面だから、あと10円」と言ってさらにせびります。やむなく熊さんは支払い、話は続きます。
ところが亀坊は、「そのあと、お母っさんが自分に小遣いをくれて外へ遊びに行かせたので、それ以上は分からない」と言い出します。熊さんは「どうして肝心なところで外へ出たんだ」と怒りますが、亀坊は「気になって戻ってきて、障子の隙間から覗いた」と言い、また10円を要求します。熊さんがさらに払うと、亀坊はついに「その男の人は、いつも来る按摩(あんま)さんだった」とオチをつけて、そそくさと外へ遊びに行ってしまいます。
熊さんが女房にこの話をすると、女房は呆れながらも「うちの子は賢い、近所の子より知恵が回る」と感心します。しかし熊さんは「ずる賢いだけで知恵者じゃない」と不満を漏らし、自分が知恵者と認める人物の例として、真田幸村の少年時代の逸話を語り始めます。
その話は、真田幸村が14歳のとき、敵に城を囲まれた際に機転を利かせ、敵軍の旗印である「永楽通宝」の旗を掲げて夜襲を仕掛け、敵の混乱を誘って脱出したというもの。その勇気と知略に感動し、真田家の家紋が六連銭になったという逸話です。熊さんは「うちのガキとは違う」と嘆きます。
そこへ亀坊が帰ってきます。熊さんが「金を返せ」と言うと、亀坊は「講釈を聞きに行って全部使っちゃった」と返します。何の講釈かと問うと、「真田三代記」と言い、さっき熊さんが話していた内容をすらすらと語り始めます。
亀坊は「六連銭ってどんな紋?」と聞き、熊さんが「上に三つ、下に三つの丸を並べる」と説明します。亀坊は「見てみたい」と言い、家の中の硬貨をかき集めて並べます。すると今度は「自分が並べてみる」と言って銭をすべて持ち出し、そのまま表へ飛び出していきます。
熊さんは、「この野郎、また講釈を聞きに行く気か!」と怒鳴りますが、亀坊は「今度は焼き芋を買ってくるんだよ」と答えます。熊さんは苦笑しながら、「ああ、いけねえ、うちの真田も薩摩に落ちた」と、先の真田幸村の話になぞらえたオチで幕を閉じます。
この噺は、子どもならではの言葉遊びや策略を通じて、大人を振り回す姿を滑稽に描いています。同時に、講釈や歴史談義も巧みに取り入れられ、落語らしい教養と笑いが融合した演目です。親子の愛嬌あるやりとりと、子どものずる賢さが魅力となっており、古典落語の中でも人気のある一席です。
◎演目視聴◎
こちらでは『三代目古今亭志ん朝』と『五代目古今亭志ん生』の『搗屋幸兵衛』をご紹介いたします。
三代目古今亭志ん朝(1938-2001)
『真田小僧』(27分40秒)