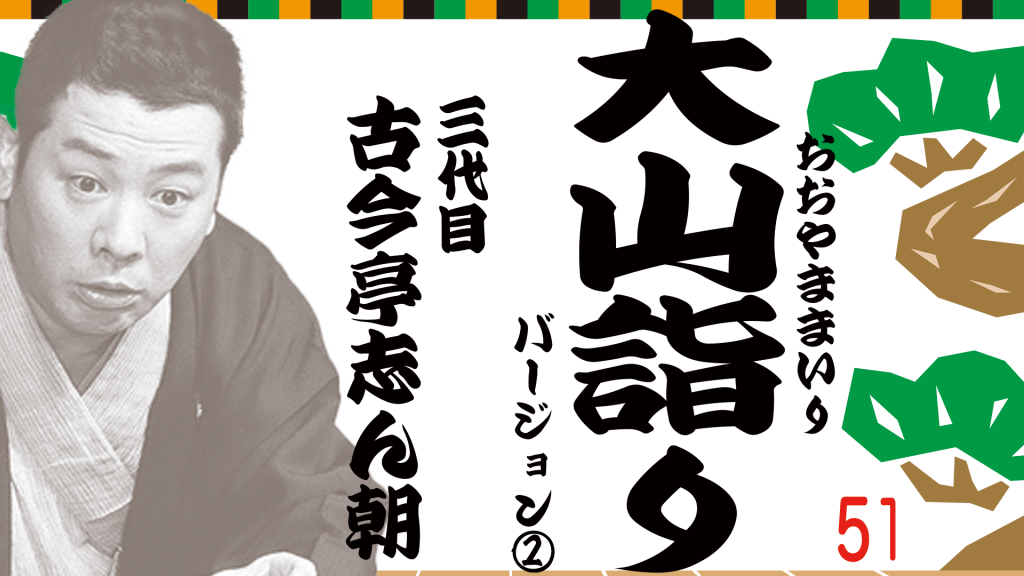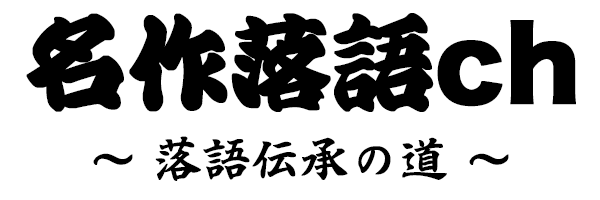◎あらすじ◎
落語「大山詣り」は、江戸庶民の信仰と旅の風習、そして人情と笑いが詰まった一席です。舞台は江戸の長屋。住人たちが、神奈川県の大山(おおやま)に詣でることを決めます。これは当時流行した庶民の信仰登山で、講(こう)という集団で行動し、神仏への祈願と観光を兼ねた旅でした。
先達(せんだつ=引率役)の吉兵衛さんは、酒癖が悪く喧嘩っ早い熊五郎(熊さん)に頭を悩ませます。例年の大山詣りでも問題を起こしていたため、今回は留守番を頼もうとしますが、熊さんは自分だけ仲間外れにされるのは嫌だと必死に食い下がります。「今年こそは絶対に喧嘩はしない」と誓い、吉兵衛も「喧嘩をしたら坊主頭にする」という約束を条件に、しぶしぶ連れていくことに。
旅は順調で、大山詣りを済ませた一行は、帰路に藤沢や神奈川宿へ立ち寄ります。江戸も近いある晩、気が緩んだ熊さんが酒を飲みすぎ、やはり大暴れ。宿屋で大立ち回りを演じ、数人が負傷する騒ぎに。翌朝、熊さんが爆睡している間に、怒った仲間たちが彼の頭を剃って丸坊主にしてしまいます。
熊さんが目覚めると、宿の女中たちは「坊さんが起きた」と笑いながら騒ぎます。鏡を見て唖然とする熊さん、復讐を決意し、急ぎ江戸へ戻ります。途中で旅の仲間たちを追い抜き、先に長屋に帰りついた熊さんは、女房たちを集めて大芝居を打ちます。「舟で帰る途中に嵐に遭い、自分以外はみな溺死した。供養のために坊主になった」と涙ながらに語り、見事に信じ込ませるのです。
涙にくれる女房たちの中で、吉兵衛の女房だけは「ホラ熊」と呼ばれる熊さんの虚言癖を見抜いています。しかし、熊さんが手ぬぐいを取ってつるつる頭を見せると、「丸坊主になるほどなら真実に違いない」と信じ込み、全員が泣き崩れます。
そして熊さんは「それほど亭主が恋しいなら尼になって供養するのが一番」と説き伏せ、なんと女房たちを全員坊主頭にさせてしまいます。
しばらくして、何も知らない男たちがのんびり旅の余韻を楽しみながら長屋に帰ってくると、目の前には念仏を唱える坊主頭の女房たち。中央には得意げな熊さん。事情を聞いて驚く男たちに、吉兵衛が「お山は晴天、家に帰ればみんな無事で、お毛が(怪我)がなかった」と洒落でまとめ、騒動は笑いに包まれて幕を閉じます。
「大山詣り」は、熊さんの図太さと機転、そして長屋の人情味あふれる暮らしが絶妙に描かれた滑稽噺。信仰心と騒動、そして最後はユーモアで包み込むという、落語ならではの魅力にあふれた名作です。
◎演目視聴◎
こちらでは『三代目古今亭志ん朝』の『大山詣り』を2本、ご紹介いたします。時と場所が変わると、同じ演目でも感じ方が異なります。ぜひお楽しみください。
三代目古今亭志ん朝(1938-2001)
『大山詣り ver.1』(30分53秒)
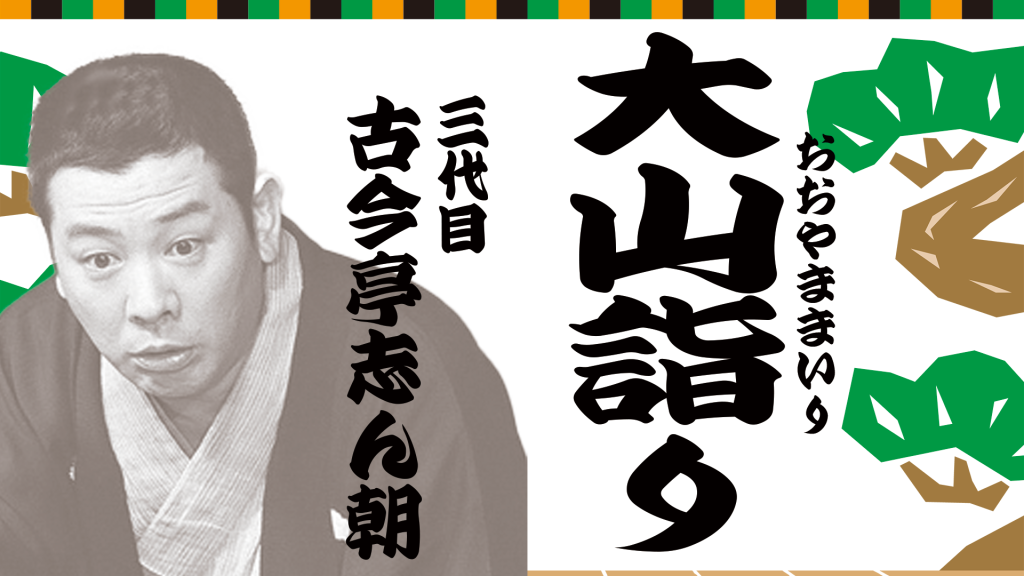
三代目古今亭志ん朝(1938-2001)
『大山詣り ver.2』(39分37秒)