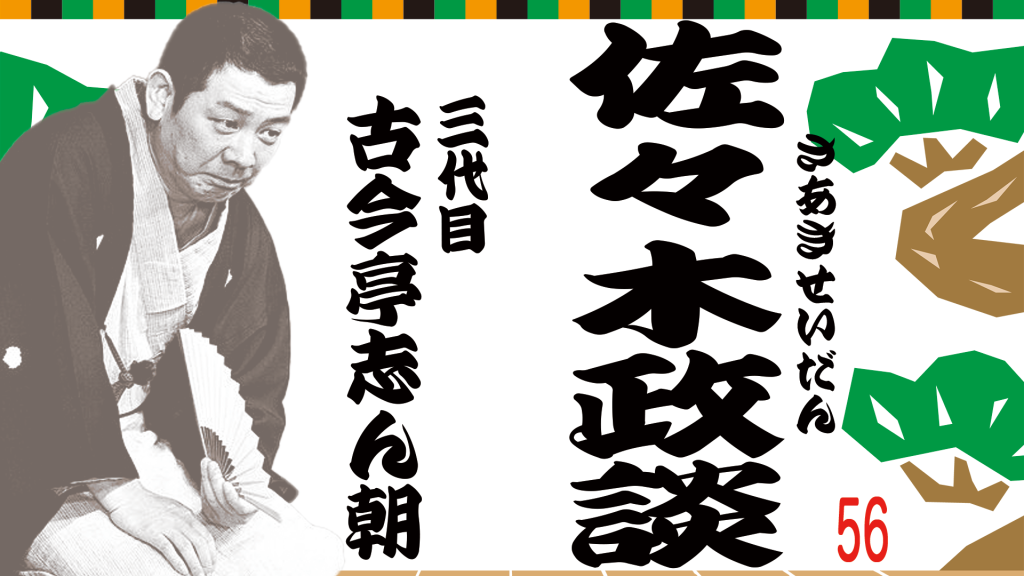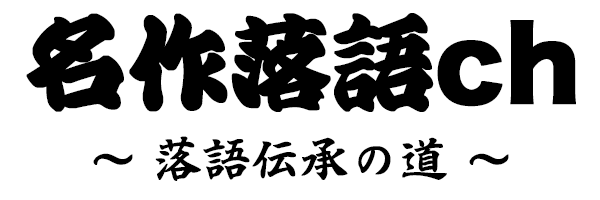◎あらすじ◎
落語の演目「佐々木政談」は、江戸時代の南町奉行・佐々木信濃守を主人公にした、機知と風刺に富んだユーモラスな物語です。この噺は、町人の子どもながら聡明な少年と奉行とのやりとりを通じて、庶民の知恵や観察力の豊かさを描いています。
物語は、奉行の佐々木信濃守が市中をお忍びで見回りしている場面から始まります。ある日、彼は新橋の竹川町で子どもたちが「お奉行ごっこ」をして遊んでいるのに出くわします。興味を引かれて立ち止まって観察していると、奉行役の子どもが自分と同じ「佐々木信濃守」と名乗っており、喧嘩の仲裁という「白州ごっこ」の真っ最中でした。
この少年奉行、名を四郎吉といい、ただの遊びとは思えぬほど堂々とした裁きを下します。「一から十まで『つ』が揃っているか否か」で揉める喧嘩の調停で、「そのような些細なことで上に手数をかけるのは不届き」と一喝し、最後には「五つの『つ』の一つを十に足せば全て揃う」と見事な機転で一件落着させます。
この様子に本物の佐々木信濃守はすっかり感心し、少年とその親を奉行所に呼び寄せます。町中は「本物の奉行を棒で追い払った」などと大騒ぎ。いざ奉行所に出頭した桶屋の高田綱五郎とその息子・四郎吉。父は緊張で青ざめますが、当の四郎吉はまるで平気で、堂々と奉行の前に立ちます。
奉行は四郎吉の知恵を試すように、さまざまな問いを投げかけます。例えば、「空の星の数を知っているか」という問いには「白州の砂利の数と同じく分からない」と答え、奉行をうならせます。
さらに、饅頭を与えながら「母と父、どちらが好きか」と尋ねられると、「饅頭も二つに割ったらどちらが美味しいか分からない」と機転の利いた返答でかわします。
また、「三方は四角いのになぜ三方と言うか」や、「一人でも与力というが、どういう意味か」といった抽象的な問いにも、「身分は軽いが権力をかさに着て偉そうにしているが、踏まれたらすぐ潰れる」と、風刺の効いた答えを返し、奉行所にいる与力たちを苦笑させます。
極めつけは、「屏風の絵の仙人が何と言っているか聞いてこい」という無理難題。四郎吉は真顔で戻ってきて、「佐々木信濃守は馬鹿だと言ってました」と平然と返し、奉行を大笑いさせるのです。
このやりとりに感服した佐々木信濃守は、後に四郎吉が十五歳になると自らの近習として取り立てたと語られ、「佐々木政談」は幕を閉じます。
この噺は、江戸庶民の機知や人間観察力の豊かさをユーモアたっぷりに描いており、単なる子どもの遊びの中に、大人顔負けの洞察力と自由な発想が光る、知恵比べの妙が魅力の一席です。
◎演目視聴◎
こちらでは『三代目古今亭志ん朝』の『佐々木政談』をご紹介いたします。
三代目古今亭志ん朝(1938-2001)
『佐々木政談』(31分52秒)