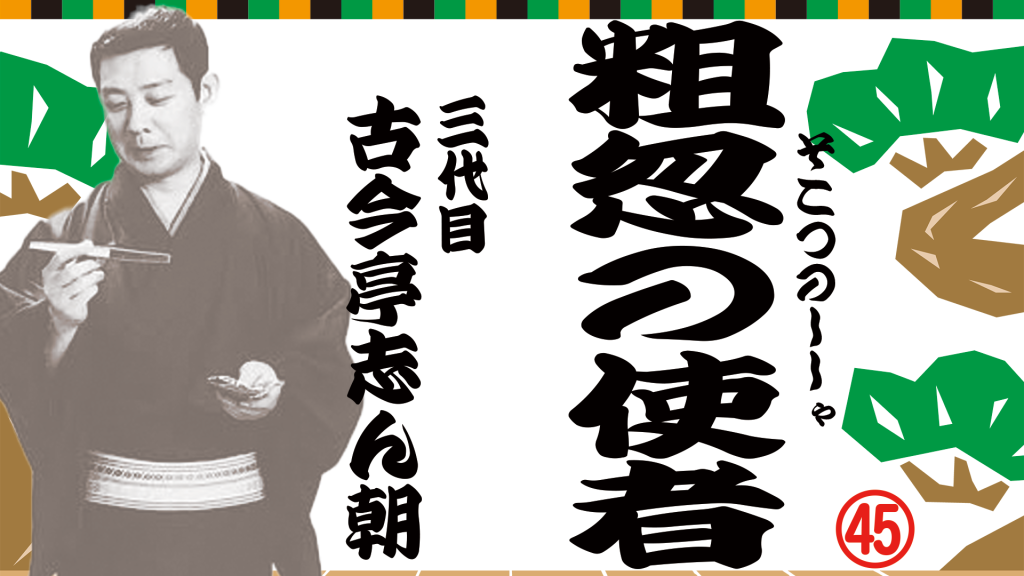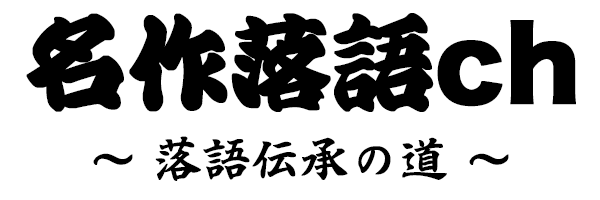◎あらすじ◎
落語「粗忽の使者」は、粗忽者(そそっかしい人間)が巻き起こす騒動を、洒落とユーモアで描いた古典落語です。この噺の主人公は、ある大名家・杉平柾目正(すぎひら まさめのしょう)に仕える家来、地武太治部右衛門(じぶた じぶえもん)という侍。名前からして変わったこの人物は、大変な粗忽者ですが、それがかえって殿様の気に入りで、日頃から家中の笑いの種になっていました。
ある日、この治部右衛門の評判を聞きつけた親戚筋の赤井御門守(あかい ごもんのかみ)が、「その奇妙な侍を見たい」と申し出ます。殿様も面白がり、治部右衛門を正式な使者として赤井家に派遣することにします。
当の治部右衛門は事情を知らず、朝から大はしゃぎ。まず「別当(べっとう)」を「弁当(べんとう)」と聞き違え、朝から大騒ぎ。ようやく馬にまたがって出発するも、その道中も粗忽ぶりを発揮します。
さて、使者として赤井家に到着した治部右衛門。しかし、家老・田中三太夫(たなか さんだゆう)から正式な口上を求められると、なんと「口上を忘れた」と言い出します。驚く家中。治部右衛門は「子どものころから、忘れたことは尻をひねられると思い出す」と奇妙な習慣を明かし、三太夫は仕方なくひねってみるのですが、長年の習慣で尻は鱗のように硬くなり、効果なし。
三太夫は「指の力がある者を探してくる」と席を外します。そこへ偶然通りかかった大工の留っこが騒動を聞きつけ、「自分がひねってやろう」と申し出ます。困った三太夫は、急ごしらえで留っこを「中田留太夫(なかだ とめだゆう)」なる侍に仕立てあげ、お使者の間へ送り込みます。
口上の礼儀を教えられたものの、いざ治部右衛門と対面すると、留太夫は素に戻り「さあケツ出せ。後ろ向くなよ」と荒っぽい口調で命令。実は留太夫は、道具を使うことを考え、隠し持っていた大きなペンチ「閻魔」で治部右衛門の尻をひねります。
「痛み耐えがたし!」と叫ぶ治部右衛門。何度もひねられるうちに「思い出してござる!」と叫びます。
安堵する三太夫がふすまを開けて問いかけます。「して、口上は?」
すると治部右衛門は、まさかの一言。「屋敷を出る折、聞かずにまいった」と。
つまり、何も聞かされずにやって来たのです。忘れたのではなく、最初から知らなかったというオチ。手間をかけた騒動は、全くの無駄骨であったことが判明します。
この噺は、落語ならではの「粗忽者」の描写と、身分を超えた人物たちのユーモラスなやりとり、そして意外なオチが魅力です。治部右衛門の真面目さと、留っこの機転が噛み合わない滑稽さが、観客に笑いと驚きを与えます。
「粗忽の使者」は、古典落語の中でも粗忽噺の代表的な演目で、人間の思い込みや早とちりの面白さを見事に描いた名作です。
◎演目視聴◎
こちらでは『三代目古今亭志ん朝』の『粗忽の使者』をご紹介いたします。
三代目古今亭志ん朝(1938-2001)
『粗忽の使者』(29分09秒)