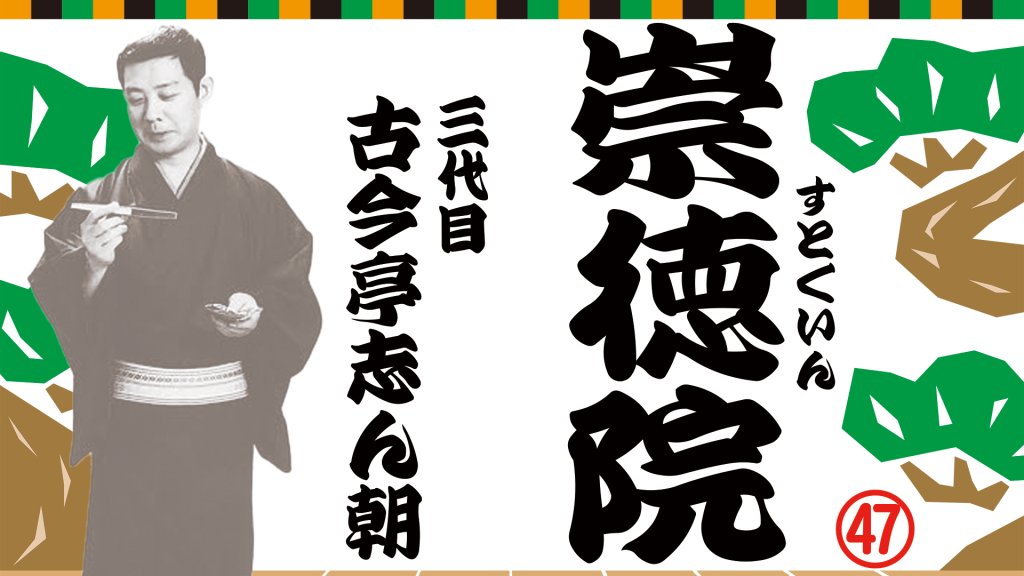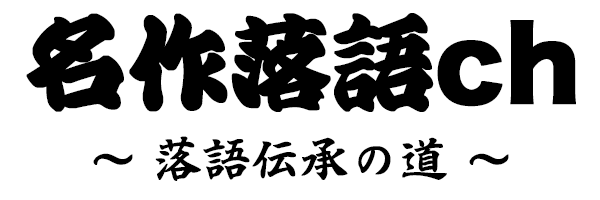◎あらすじ◎
江戸のある大店の若旦那が、原因不明の病で寝込んでしまう。名医の診断では「気の病」すなわち恋わずらいだという。親身になって世話を焼く店の大旦那は、若旦那が誰にも悩みを打ち明けず心を閉ざしていることに困り、昔からの馴染みである町人の熊五郎に相談を持ちかける。熊五郎ならば気軽に話を聞き出せるかもしれないと期待されたのだ。
熊五郎が若旦那を訪ねて話を聞くと、どうやら病の原因は恋煩い。20日ほど前に清水観音への参詣の帰り道、茶店で見かけた美しい娘に一目惚れしてしまったのだ。別れ際に娘から手渡されたのは一枚の紙片。そこには和歌「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」とだけ書かれていた。これは崇徳院の有名な和歌で、下の句「割れても末に逢はんとぞ思ふ」と合わせると「いかに離れ離れになろうとも、必ず再会し結ばれたい」という意味になる。娘の思いに応えられないもどかしさと再会の望みが絶たれたことで、若旦那は心を病んでしまったのだった。
大旦那は熊五郎に娘探しを依頼し、成功すれば借金を帳消しにし、三軒長屋まで進呈すると大判振る舞いの約束をする。熊五郎は意気込んで江戸中を探し回るが、手がかりは「水も滴るような美人」と「崇徳院の和歌」のみ。水が滴るという表現にとらわれた熊五郎は、「水のたれるような女の人」を手がかりに人々に聞き込みを始めるが、情報は得られない。
行き詰まった熊五郎は、女房の助言で「崇徳院の歌」を大声で詠いながら人が集まりやすい風呂屋や床屋を回る作戦に出る。だが子どもや犬にからかわれ、空振りの連続。36軒の風呂屋、18軒の床屋を回っても見つからず、疲れ果てて同じ床屋に二度目の来店をしてしまう。
そこで偶然、もう一人の登場人物と出会う。町の鳶職の頭(かしら)であるこの男も、娘に崇徳院の歌を贈られたことで恋に落ち、相手を探して四国まで旅をしようとしていたという。話は一致しているが、互いに自分が先に探し当てると意地を張り合い、口論から鏡を割ってしまう。
床屋の主人が「どうしてくれるんだ、鏡を割っちまって」と嘆くと、頭はにっこりしてこう返す。「なに、心配いらねえ。割れても末に買わんとぞ思う」――崇徳院の和歌をもじった、洒落のきいたオチで物語は幕を閉じる。
恋と詩をめぐる騒動を描いた人情噺です。
◎演目視聴◎
三代目古今亭志ん朝(1938-2001)
『崇徳院』(35分22秒)